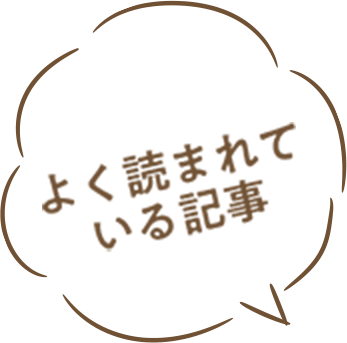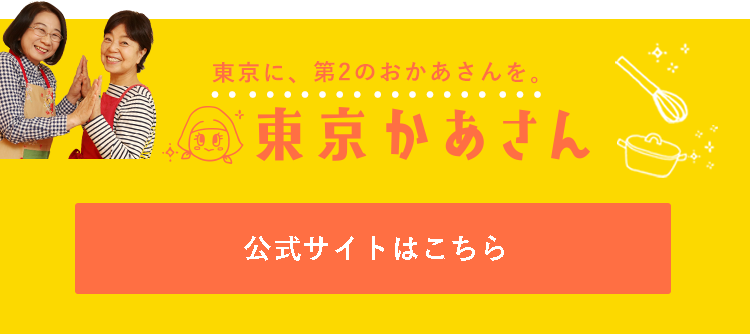2021.10.22
ベビーシッターに使える補助金・助成制度まとめ!詳細や申請方法まで解説

仕事でどうしても家を空けなければいけない時、自宅で子どものお世話をしてくれるベビーシッター。便利なサービスである一方、料金の相場や支援制度がわからずハードルの高さを感じている方も少なくないでしょう。今回はそんなベビーシッターの補助金の種類や相場について、詳しくご紹介していきます。
目次
ベビーシッターに使える!お得な補助金・助成制度とは?

仕事などでどうしても育児ができない時、自宅で子どものお世話をしてくれるベビーシッター。共働き世帯やひとり親世帯にとっても非常に便利なサービスですが、料金が高そうというイメージを持つ方も多いですよね。
でも実は、ベビーシッターは、さまざまな補助金・助成制度を利用できるんです。補助金を上手に使えば、お得にベビーシッターサービスをお願いすることもできます。さっそくどのような補助金があるのか、チェックしてみましょう。
乳幼児~小3まで対象の補助金◎内閣府ベビーシッター割引券

内内閣府ベビーシッター割引券では、児童1人につき1回のベビーシッター利用で、最大4,400円の補助金を受けることが可能です。
補助金額
内閣府ベビーシッター割引券とは、内閣府の承認事業主となっている企業の従業員が利用できる補助金制度です。ベビーシッターの利用に使える2,200円分の割引券を、対象の児童1人につき1日に2枚まで使用できます。
ただし多胎児の場合は、2人で最大9,000円まで、3人以上では最大18,000円と制度が異なるので注意が必要です。
1回の利用で2,200円を超える場合にのみ使用でき、1家庭では1ヶ月に24枚までの使用と定められています。この制度を活用すれば、ベビーシッター利用時に最大で一ヶ月52,800円の補助金を受けることが可能です。
高いと感じていたベビーシッターの料金も、これだけ補助を受けられればお願いしやすいですよね。
内閣府ベビーシッター割引券の利用条件とは?
補助金受け取りの対象となる児童は、乳幼児または小学校3年生までの児童。身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けている場合は、小学校6年生までの児童が対象です。
保護者の就労や病気療養、または、ひとり親家庭で就労が困難な状況であることが利用条件となっています。自宅でのお世話以外にも、家庭から保育施設等への送迎(交通費は別途)にも利用可能です。
内閣府ベビーシッター割引券の申請方法
内閣府ベビーシッター割引券は、個人が申込をするのではなく、企業が申請をすることで従業員が利用できる支援制度です。まずは自分の働く会社が割引券承認事業主となっているかを確認し、承認されている場合は会社へ申請しましょう。
まだ承認を受けていない企業が申請をする場合は、全国保育サービス協会への必要書類提出で、申請が可能です。
ベビーシッターをお得に利用!自治体独自の補助金に注目

ベビーシッターの補助金には、自治体ごとに利用できるものもあります。自治体が独自に支援している補助金になるので、その内容は自治体によって大きく異なることがほとんど。ベビーシッターを利用する場合は、自分が住む自治体に補助金があるかどうかを確認するのもおすすめです。
東京都で利用できるベビーシッターの補助金
東京都では、待機児童対策としてのベビーシッター利用支援事業を進めています。保育所の0~2歳クラスに相当する待機児童の保護者や、1年間の育児休業後に1歳の誕生日から復職する保護者がベビーシッター利用時に使用できる補助金です。
認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合に限り、1時間150円(年会費やオプションは別途)でベビーシッターを利用できます。ただし東京都内でも対象となる市区町村が限定されているので、自治体の子育て支援課などに問い合わせてみると良いでしょう。
2021年に法改正!ベビーシッターの補助金は非課税でお得に

2021年に税制が改正されたことで、ベビーシッターの補助金は非課税となりました。以前は公費で負担された助成金が、雑所得という扱いで課税対象となっていましたが、現在では非課税となり、所得税や住民税の増税を抑えることができます。
例えば5,000円のベビーシッターサービスを利用して、4,400円分の割引券を利用した場合、今まではその4,400円がそのまま雑所得として利用者に課税されていたのです。ベビーシッターの利用料金は600円ですが、課税分で金額がかさんでしまうケースも。
しかしベビーシッターの補助金が非課税になったことで、ベビーシッターの利用料金がリーズナブルになったと言えるでしょう。
年間の給与収入が500万円の場合、21万円も課税額が下がるという算出結果もあるほどなので、共働き世帯にとって、ベビーシッターをより利用しやすくなったということですね。
補助金なしでもお得◎東京かあさんが育児・家事をサポート

ベビーシッターといえば子どものお世話をお願いできるサービスですが、基本的には育児のみを行うのがベビーシッターの仕事と考えられています。でも中には、ベビーシッターと家事を両立してお願いできるサービスもあるんです。
安心して子供を任せられる専任制
東京かあさんは、ご近所で第二のお母さんを持つことができるサービスです。担当のお母さんができる事であれば、何をお願いしてもOK。ベビーシッターをお願いして、もし子どもが寝てしまったら、掃除や料理なども両立してお任せできます。
また専任制のサービスなので、毎回担当の方にやることを説明する必要もなし。利用すればするほどに、阿吽の呼吸でさまざまなお手伝いをお願いできます。
買い物の代行や収納の整理などの家事だけでなく、時には話し相手としてほっと一息つけるひとときを提供してくれることも。この柔軟性が東京かあさんの大きな魅力なんです。
補助金なしでもベビーシッターの相場よりリーズナブル
ベビーシッターを利用する際の相場は、サービスによって大きく異なりますが、1時間で2,000円~4,000円程度のところが多いです。
もちろんサービス内容によって異なりますが、ベビーシッター会社を通して契約をする場合は、入会金や年会費がかかるケースも。他には指名料、子どもの人数に応じたオプション料金などが必要な場合もあります。
東京かあさんは利用した分だけ支払えばOKの従量料金を採用。1回あたり1時間以上、月合計8時間以上の利用なら自由な組み合わせで定期スケジュールを組めます。
料金は、1回あたりの利用時間が増えるほど割安になり、1時間2,530円(税込)~の利用が可能です。
また、1回限定「お見合いパック」の価格も3時間、訪問費込みで7,480円(税込)とリーズナブルなので、自分と相性が合うお母さんを見つけられるのも嬉しいポイントですよね。入会金と一律880円(税込)の訪問費以外にかかるオプションは、鍵のお預かり(月額1,100円・税込)と深夜早朝料金(1時間あたり440円・税込)。わかりやすい料金体系で、気軽に使いやすいサービスとなっています。
補助金で上手に活用しよう!子育て世帯を支えるベビーシッター

高い費用がかかるというイメージのベビーシッターですが、補助金や支援制度を上手に活用すればリーズナブルにサービスを利用できます。共働き世帯や待機児童がいる世帯の強い味方となってくれるベビーシッター。どのような補助金があるのかをしっかりと理解して、安心して任せられるベビーシッターを探してみてください。